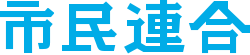なぜ、介護保険は使いづらいのか
市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰 小竹雅子
【2024.10.11】

25年目を迎えた介護保険制度
2000年度からサービスがはじまった介護保険制度は、法改正と介護報酬・基準の改定という複雑な見直しを積み重ねながら、25年目を迎えました。
市民福祉情報オフィス・ハスカップは、2003年から介護保険制度をテーマに電話相談やセミナーの開催、制度の見直しを審議する社会保障審議会の傍聴など、市民活動を続けています。
活動のなかで繰り返し感じるのは、多くの人にとって介護が必要な時期にならないと、制度に関心が持てない、という現実です。それだけが理由ではありませんが、介護を必要とする本人や家族などの介護者、現場を支える介護労働者の声はほとんど注目されず、政策決定にも反映されない構図が続いています。
利用者の8割は「在宅」を選択
介護保険のサービスは大きく「在宅」と「施設」に分かれます。2023年度末、介護が必要と認定された708万人のうち、実際に給付を受けている人(受給者)は561万人です。受給者の464万人、8割を超える人たちが「在宅」を選んでいます。
なお、「在宅」には認知症グループホームや特定施設(介護付き有料老人ホーム、一部の「サービス付き高齢者向け住宅」)が含まれます。これらのサービスは「居住系」、「高齢者の住まい」とも呼ばれ、食費と居住費(入居一時金の場合もあります)は別料金になります。
「施設」に分類されるのは生活施設の特別養護老人ホーム、医療施設の老人保健施設、介護医療院(旧・介護療養病床)の3施設だけで、利用者は97万人です。「施設」の場合、低所得の利用者には食費と居住費を補助する「補足給付」(特定入所者介護サービス費)があります。
増え続ける介護保険料
介護保険に加入している被保険者は7,460万人で、40~64歳の現役世代(第2号被保険者)が4,190万人、65歳以上の高齢世代(第1号被保険者)が3,579万人です。
第1号介護保険料は、保険者である市区町村(区は東京23区です)が介護保険事業計画にもとづき計算し、年金収入が月1.5万円(年間18万円)以上の3,219万人は天引き(特別徴収)されています。
制度の会計期間は3年1期で、第1号介護保険料(全国平均月額)は第1期(2000~2002年度)の2,911円から第9期(2024~2026年度)の6,225円と倍増しました。所得に応じた負担段階の設定はありますが、3年ごとに増える介護保険料は年金受給者の手取り額を減らしています。
介護保険制度の費用は、医療保険の窓口負担と同じように利用者の原則1割負担の利用料を引いた残りを給付費として、介護保険料と税金で折半しています。
少子高齢化の進行とともに介護を必要とする人が増え、費用も上昇するのは当然です。しかし、介護保険料の現役世代と高齢世代の分担は人口比率で決まるため、費用が増えなくても高齢者の第1号介護保険料が上昇する設計には過酷なものがあります。社会保障審議会では2000年代から、保険者サイドの委員が公費負担(税金)を増やすことを繰り返し求めていますが、ほぼ黙殺されています。
「骨太方針」と在宅サービスの抑制
介護保険制度は「利用者本位」を掲げますが、在宅サービスで人気が高いのはホームヘルプ・サービス(訪問介護)、デイサービス(通所介護)、福祉用具レンタルです。施設サービスでは、特別養護老人ホームが待機者を増やしていました。
しかし、政府は2000年代から経済財政諮問会議の意見をもとに「介護保険制度改革」として給付抑制を重ねました。
小泉政権は2004年の法改正で「予防重視型システムへの転換」として、認定を要支援と要介護に、給付を予防給付と介護給付に分割し、介護の必要度が低いと言われる要支援(現在は要支援1と2)の人への在宅サービスを縮小しました(経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004)。
安倍政権は「介護予防の推進」で、要介護者を「7人に1人」から「10人に1人」にする目標を掲げ、市区町村事業(地域支援事業)で、認定を受けていない高齢者を対象に「介護予防事業」への参加を奨励し、2024年現在まで続いています(経済財政改革の基本方針2007)。
特別養護老人ホームの利用制限
2014年の法改正では「地域包括ケアシステムの構築」が掲げられ、特別養護老人ホームが利用できるのは要介護3以上に「重点化」され、要介護1と2は「特例入所」とハードルが高くなりました。当時、特別養護老人ホームを希望する待機者は52万人を数えました。また、利用者の平均認定ランクはすでに、要介護3を超えていました。改正後、待機者は29万人まで減り、数字の上では半減しました。
「特例入所」の条件は、認知症や精神障害などで在宅生活が困難な場合、同居家族による深刻な虐待が疑われる場合、ひとり暮らしや高齢夫婦世帯で家族の支援が期待できない場合などですが、利用できるかどうかは市区町村や特別養護老人ホームの裁量次第となりました。
「サービス付き高齢者向け住宅」の激増
特別養護老人ホームは在宅介護者にとって「最後の砦」とも呼ばれましたが、利用制限が加えられた結果、「サービス付き高齢者向け住宅」(通称・サ高住)に住み替える人が増えました。
厚生労働省と国土交通省が共同企画したサ高住は、建設補助金がつく賃貸住宅で、付随するサービスは「相談支援」と「安否確認」のふたつです。
多くの人が誤解するのは、サ高住の運営法人のなかにホームヘルプ・サービスやデイサービスの事業所を併設しているケースがあり、サービスがパックされている「施設」だと思ってしまうことです。提供するのは在宅サービスなので、利用料は別に払います。また、「フリープラン」とも呼ばれる介護保険外サービスの提供もあり、こちらも別料金で、全額利用者の負担です。
2011年に30棟0.3万戸からスタートしたサ高住は、2024年には8,307棟28.8万戸と増加の一途です。入居者は自宅からの転居が半数を超え、特別養護老人ホームに入居できない要支援認定と要介護1と2の認定者が多いと報告されています。
市区町村事業に“移す”という給付抑制の手法
2011年の法改正では、要支援認定者(要支援1、2)のホームヘルプ・サービスとデイサービスを給付からはずし、地域支援事業に移すことになりました。介護保険は認定を受けた人に給付を受ける権利(受給権)を認めますが、ニーズの高いサービスが給付からはずされたのです。しかも、この削減計画は6年がかりで、多くの人が気づかないうちに、2017年度末に「完全実施」されました。
地域支援事業の財源は介護保険料と税金です。とはいえ、認定者に個別給付されるサービスとは異なり、市区町村に事業費が渡されます。サービスを提供するのは市区町村裁量の委託事業所です。介護保険の法定基準をクリアした指定事業所だけでなく、民間会社や住民団体も参入しているため、サービス内容や質にバラつきがあることは否めません。
2015年になると、経済財政諮問会議の下に経済・財政一体改革推進委員会が設置され、「軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付」について削減を検討するよう「関係審議会」に求めました(経済・財政再生計画改革工程表)。
「軽度者」の定義は不明ですが、「関係審議会」に財務省の財政制度等審議会が参加し、要介護1と2を「軽度者」と呼び、ホームヘルプ・サービスとデイサービスの地域支援事業への移行などを求めました(2021年度予算の編成等に関する建議)。
厚生労働省の社会保障審議会では、要介護認定者の主要在宅サービスの削減と利用者負担の増加については、両論併記と審議継続の報告が繰り返されました。
しかし、岸田政権が2024年6月に公表した『骨太方針2024』で、「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」について、「第10期介護保険事業計画期間の開始の前までに検討を行い、結論を得る」ことを求めました。現在は第9期なので、遅くとも2026年度中に結論を出せということです。
市区町村事業に“留める” という給付抑制の手法
社会保障審議会は在宅サービスの削減に抵抗していますが、法改正に至らない細かい抑制策は容認しています。とくに利用者や高齢介護者にダメージが大きいのは、ホームヘルプ・サービスの「生活援助」へのバッシングで、提供時間の短縮、利用回数の制限など、利用できないわけではないが「使えない」という見直しを積み重ねています。
2024年の省令改正では、地域支援事業を利用する要支援認定者(要支援1と2)が、要介護認定(要介護1~2)と介護の必要度が高くなっても、「本人の希望」により地域支援事業にとどまることができる、つまり、給付を望まない「継続利用要介護者」を増やす見直しが行われました。
新たに介護保険を利用する人や介護家族は、これまでの経緯をほとんど知りません。市区町村やケアマネジャーに勧められるままに「継続利用要介護者」になる可能性は高くなります。また、ホームヘルプ・サービスの基本報酬引き下げとホームヘルパー不足のなか、事業所の閉鎖・倒産報道が相次いでいます。給付を提供する指定事業所がないので、地域支援事業の「継続利用要介護者」を増やす、という事態も十分に予測されます。
「家族介護」への逆流
介護保険を利用するには、認定を申し込み、訪問調査を受け、約1か月、結果を待たなければなりません。とても面倒な手続きであるにもかかわらず、認定者の76%しか実際にサービスを利用していません。厚生労働省は「家族介護でなんとかやっていける」、「介護が必要な本人でなんとかやっていける」からだという説明をくり返します。
2015年、安倍政権は「介護離職ゼロ」を打ち出しましたが、ホームヘルプ・サービスの抑制策は続き、介護のために仕事を辞める人は毎年10万人というペースが続いています。
厚生労働省は「介護離職」防止のため育児・介護休業法の改正をしましたが、休職して家族介護を担う労働者を増やすのでは、無償介護の負担は軽減されません。経済産業省は「ビジネスケアラー」の増加にともなう経済的損失は約9兆円として、経営者に「両立支援」を求めるガイドラインを出しましたが、「介護保険外サービスを積極的に活用する」ことを勧める始末です。
在宅サービス削減がもたらしたのは…
介護保険のスタート時、高齢者の暮らしは「三世代同居」が3割を超えていました。四半世紀が過ぎたいま、「三世代同居」は三分の一に減り、ひとり暮らしの「単独世帯」、「高齢夫婦世帯」が増えています。気になるのは「親と未婚の子のみの世帯」の増加で、「8050問題」と呼ばれる無職のミドル代の課題をはらんでいます。
今年になり、総務省は「ごみ屋敷」調査で、単身世帯が約6割で、65歳以上の高齢者が半数を超え、「居住者の約7割は健康面や経済面の課題(要介護、認知症、精神疾患、生活困窮等)を抱えている」と報告しました。警察庁は2024年度上半期の半年間で「自宅において死亡した一人暮らしの者」は37,227人、65歳以上の高齢者が28,330人と約8割になることを公表しました。
「生活支援」に重点化した制度を
高齢者の所得や貯蓄の格差は大きく、低所得の高齢者は近未来への不安を抱えています。制度の見直しでは、「自立支援」という言葉がよく使われていますが、病気や障害があってもその人らしく暮らす「自立」を支えるのではなく、必要な給付から離脱する「自立」ばかりが求められています。
介護が必要と認定を受ける人の約8割は80歳以上です。高齢化は2040年まで続き、後期高齢者が増える、ひとり暮らしが増える、認知症は軽度も含めて1,197万人になる、と推計されています。
介護労働者は215万人ですが、2040年までに57万人増やす必要があります。しかし、2023年の有効求人倍率は、ホームヘルパーは14.1倍、施設などの介護職員は3.2倍で、全職業計の1.31倍に比べ、異常ともいえる人手不足です。
大変、残念なことに、10月4日の石破総理大臣の所信表明演説では、社会保障制度はもとより、介護保険制度の危機的状況への言及はまったくありませんでした。
まもなく衆議院選挙が公示されますが、本格的な超高齢社会に「誠心誠意」向きあう政治家を求めたいものです。
(2024.10.11脱稿)
--------------------------------------------------
小竹雅子(おだけ・まさこ)市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰
2003年より「市民福祉情報オフィス・ハスカップ」(http://haskap.net/)主宰。介護保険制度をテーマに電話相談やセミナーを企画するほか、制度改定をまとめた『ハスカップ・レポート』を毎年発行。社会保障審議会の傍聴をもとに、メールマガジン『市民福祉情報』(2024年10月現在、1279号)を無料配信中。著書『総介護社会 ―介護保険から問い直す』(岩波新書、2018年)、エッセイ集『「市民活動家」は気恥ずかしい でも、こんな社会で大丈夫?』(現代書館、2023年)ほか。