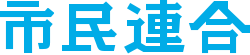社会運動は野党共闘の基盤、
社会運動と野党選挙共闘は両輪である。
宮田和保(「戦争をさせない市民の風・北海道」会員)【2022.9】

「戦争をさせない市民の風・北海道」(略称「市民の風」)は、安倍政権による安保法制・特定秘密保護法などの閣議決定・立法化によって日本を戦争できる体制につくりかえようとする、このことをやめさせるために、2015年末の北海道補選(五区)での立憲野党の統一をめざすことを機に、設立された。その生誕において野党共闘を追求・実現することを役割としている。
ところで、昨年の総選挙では野党共闘が不十分ながらも成立したが、それは十分な成果を発揮したとはいえなかった。北海道も例外的ではない。与党である自民・公明党を追いつめることができず、一定の後退を強いられた。また、今年7月の参議院選挙では、市民の風を介にして、立憲野党である立憲・共産・社民などの「政策協定」を形のうえでは実現することができた。しかし、それ以上のものではなかった。だから、北海道の議員定数3人のなかで、立憲民主2名、共産党1名、国民民主1名、というように野党内の乱立状態での選挙戦をむかえ、結果は2議席あった立憲民主は1議席、共産党は議席におよばず、全体としては後退であった。
このような参議院選挙の結果をみて、「やっぱり」という気持ちが支配したのは、北海道だけでなく、全国的にもそうでなかったかと推測される。「やっぱり」とは、野党共闘が厳しい状況にあるとおもいつつ、それを否定して奮闘・努力して難局の克服を期待する、だが、結果としてこの期待が否定されて実らなかった、このようなときの心の動きである。この兆候は、昨年の衆議院選挙が終わったときに潜在していたのであり、これが顕在化したといえよう。こうした雰囲気が、直接に口には出さなくとも、「市民の風」のメンバーのなかにも漂っていたようである(ただし筆者は市民の風に加入してまだ一年未満にすぎず、個人的な感触である)。
だからこそ、私たちは、野党共闘を追求しながら、これを追求するからこそ、この数年間で一定の成果をあげた野党共闘の成立条件をみつめなおさなければならなかった。それが前回の市民の風での「総会」(2022年3月)のひとつの課題であった。
この条件とは、野党共闘の成立の歴史をふりかえればわかるように、社会運動であった。安倍政権による安保法制・特定秘密保護法などによる「戦争ができる日本づくり」にたいして、社会的な反対運動が全国的におきた。シールズなどの若者をふくめ、「安倍政権を許さない」とした社会運動において、立憲野党が連動し、市民と野党との共闘関係が成立した。これがマスコミにも報道され、社会的に一定程度認知されることになった。社会運動次元での市民と野党との共闘関係が、国政選挙での市民と野党との共闘(=選挙での野党共闘)として昇華され、これを実現させたのである。
だから、現在の状況を当時と比較すれば、この成立条件が相対的に後退していることがわかる。このことは、ある参議院議員から、「かつてのような市民の盛り上がりがないよね」といって「野党共闘」の実体が空洞化していることが指摘された。だから、昨年の総選挙での後退が「一本化」の出遅れなどもあるが、このことにとどまったり、このことに単純に還元するだけではすまない。立憲野党の共闘の基盤である社会的運動が相対的に弱化していたのである。だから、総理が菅であろうと岸田であろうと、自民・公明党を社会的に追い詰めることができていなかった、そのなかでの選挙であったから、菅から岸田に化粧直さえすれば自民党の勝利となったのである。
社会運動次元での市民と野党との共闘関係の基盤のうえで、国政選挙次元での市民と野党との共闘が成立する、この立場からすれば、社会運動の再構成が必要になる。土台としての市民社会のあり方――その一つに社会運動がある――が政治的な運動のあり方を制約するからである。
市民の風の「規約」には、「政治を変える」ために国政選挙に焦点をあてて野党共闘を追求する、そのために他の市民団体・諸団体を協力する、と記されているが、この規約を変更して社会的運動を強めていく方向で、この1年間議論していくことになった。議論とは、当然にも議論にたんに収束させるのではなく、社会的実践のなかで新しい方向性を探ることであり、市民の風の従来の枠組みを変更することを意味する。このことは、市民の風が社会に主体的に働きかけるだけでなく、現在の社会そのものが私たち市民の風にせまっているものである。
 社会運動の方向性をさぐろうとしているなかで、2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻・侵略があった。この侵略にたいして、札幌の市民の有志とくに若者を中心に、2月27日から毎週日曜日(午前11〜12時)札幌駅の南口でスタンディングでもって抗議の意思を表わしはじめた。市民の風のメンバーも、積極的にこれに参加することにした。若者によるスタンディングは、道労連の支援があったとはいえ、12回も継続された、しかし5月15日でやめることになった。そこで、市民の風が主催者としてこれを継承することにした。当初は緊張と不安があったが、5月22日から現在(9月1日)の時点で15回のスタンディングを続けてきており、9月いっぱいまでは継続していくことを決めている。市民の風が主催だから特別の大きな団体がバックアップしてるわけではないが、現在でも60〜100名の市民が、毎週、札幌駅南口に参加している。8月28日には民医連との共催で120名以上の参加であった。そこで活躍しているのが、市民の風に所属している音楽隊「ライブ隊」(17名)である。
社会運動の方向性をさぐろうとしているなかで、2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻・侵略があった。この侵略にたいして、札幌の市民の有志とくに若者を中心に、2月27日から毎週日曜日(午前11〜12時)札幌駅の南口でスタンディングでもって抗議の意思を表わしはじめた。市民の風のメンバーも、積極的にこれに参加することにした。若者によるスタンディングは、道労連の支援があったとはいえ、12回も継続された、しかし5月15日でやめることになった。そこで、市民の風が主催者としてこれを継承することにした。当初は緊張と不安があったが、5月22日から現在(9月1日)の時点で15回のスタンディングを続けてきており、9月いっぱいまでは継続していくことを決めている。市民の風が主催だから特別の大きな団体がバックアップしてるわけではないが、現在でも60〜100名の市民が、毎週、札幌駅南口に参加している。8月28日には民医連との共催で120名以上の参加であった。そこで活躍しているのが、市民の風に所属している音楽隊「ライブ隊」(17名)である。
 彼女ら/彼らはスタンディングにできるだけ参加し、全体の雰囲気を和ませているばかりか、また、参加者のウクライナ人・ベラルーシ人と一緒にウクライナ民謡「赤いカリーナは草原に」を歌い、通りゆく市民の目をひきつけている。また、7月11日には、ウクライナおよびベラルーシ人の5人を囲み、合計40名の市民の参加のもとで交流会を成功させた。
彼女ら/彼らはスタンディングにできるだけ参加し、全体の雰囲気を和ませているばかりか、また、参加者のウクライナ人・ベラルーシ人と一緒にウクライナ民謡「赤いカリーナは草原に」を歌い、通りゆく市民の目をひきつけている。また、7月11日には、ウクライナおよびベラルーシ人の5人を囲み、合計40名の市民の参加のもとで交流会を成功させた。
このような社会的運動は、市民の風のメンバーに、現実の社会・歴史に直接に働きかけている実感、そこからうまれる確信と誇りそして相互の連帯感を生み出している。これは選挙を媒介にした政治(さらには社会)への働きかけとは質を異にしている。
だからこそ、安倍の国葬が閣議決定したとき、市民の風のメンバー(ライブ隊)から、自発的に、「安倍の国葬に異議あり」という緊急な抗議行動が提起され(8月3日)50名ほどが集まり、そして8月31日ススキノでの抗議活動(市民の風主催)には雨天にもかかわらず125名の参加であった。そして、9月6日には、市民の風も賛同団体(15団体)として参加して「国葬に異議あり」水島朝穂講演会をおこなった。ここでの講演・運動は他の諸団体への訴えに力をいれることにした。
いままでの野党共闘の活動およびこの間の社会運動によって市民の風にたいする市民からの信頼が醸成されつつあり、また他の市民団体などとの連携が、まだ端緒的とはいえ、形成されつつある。
11月27日には「ウクライナ戦争が問うもの」というタイトルでシンポジュウム(300名規模)の開催を予定している。「市民の風」単独では難しいので、労働組合や他の市民団体の協力・連携が求められる。市民の風のメンバーが提起した「ロシアはウクライナから即時撤退せよ」署名に賛同した連合北海道、道労連、自治労北海道、道平和フォーラムなどにも協力をえて成功させなければならないが、このことは、他面では社会運動レベルでの市民と野党との共闘の萌芽・端緒を形成することを意味するであろう。
もちろん、ここに課題がないわけではない。このことについて若干だけふれておこう。
社会運動は、市民運動と労働運動などからなるが、この両者を結びつけるのは容易ではない。60・70年代の社会運動での両者の分断をどのように克服するのか、さらに、市民運動のなかで市民と野党との共闘を実現することはなおさら困難である。より具体的には次のことである。
札幌市は2030年に札幌オリンピックの誘致運動をおこなっている。住民投票で直接に賛否を問う条例システムがありながらも、自民・公明だけでなく民主市民連合(立憲民主党系)所属の市会議員全員がこの条例による「直接投票」に反対し、自民党と一緒になってオリンピックの誘致をすすめている。立憲の国会議員(=野党共闘の議員)には自民党顔負けの推進派もいるのも事実である。東京オリンピックの総括もないなかで、また「賄賂」をふくめたさまざまな問題があるにもかかわらず、だ。利益誘導で自民党と一致している、といわざるをえない。
市民の風は政党から独立しているのだから、利益誘導の札幌オリンピック誘致に関して、条例による札幌市民の意思確認の必要性を訴えるべきであろう。これは民主主義の問題である。だが、そうすると、札幌市長選挙での立憲野党の共闘は不可能であり、これがまたシコリとなって、のちのち国政レベルでの野党共闘の条件を厳しくするかもしれない。こうしたジレンマが突きつけられている。
このことは、いままでの市民の風の弱点が現われたともいえる。市民の風は、国政レベルでの議員・選挙との意見交換・交流はあるが、地方議員レベルとの意見交流はほどんどないのが実情である。中央政治を支えている地方政治は、2019年の知事選をのぞいて、野党共闘をもとめる各地域(釧路、帯広、旭川、函館、小樽、そして札幌市内の各選挙区)の取り組みにゆだねられてきた。これには限界があり、現代の社会・政治のあり方の変革をかんがえれば、中央政治主導・主義から脱却して、地方政治・地方自治のあり方をどうすべきか、どのようにこれに関与していくべきかが、市民の風にとって、今後の新たな大きな課題となる。
{以上の叙述は、市民の風・事務局の同意をえたものであるが、その最終的責任は筆者にある}